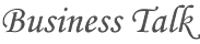真空管アンプが奏でる音色に魅せられる人は多い。真空管アンプはレコードやCDから得た微弱な電気信号を真空管を利用して増幅し、スピーカーを鳴らす装置だ。1960年代に入って、より低消費電力で、簡単な仕組みのトランジスターを使ったアンプが台頭。国内メーカーは生産中止。中高年のオーディオマニアが「手作りの音」を求めている。
真空管よみがえる 復古アンプ好調な販売 手作りの音に脚光
1996年3月23日、読売新聞
真空管--かつてはラジオやテレビ、ステレオなどほとんどの家電・音響製品に使われたおなじみの電気部品だったが、今ではIC(集積回路)やLSI(大規模集積回路)にとって代わられ、日本では、とっくに生産が打ち切られた。ところが、最近、有名メーカーが新たに真空管アンプを売り出したり、専門雑誌が特集を組んだり……と、にわかによみがえっている。遠い昔に授業で、その仕組みを学んだ中高年のオーディオマニアが、「手作りの音」を求めているのがブームの要因らしいが、あるいは、おやじたちのパソコン時代への反乱なのかも。
国内最後の真空管メーカーになったNECによると、真空管の最盛期は1950年代後半から1960年代半ば。当時、NECだけで月産10~15万本にも上っていたが、トランジスターへの切り替えが進んだ1969年に製造中止を決め、オールトランジスターテレビの出荷が本格化した1973年に生産を打ち切った。
以前は、中学校の技術家庭科で真空管の仕組みを学ぶことになっていたため、1960年代半ば生まれまでの機械好き少年だった人なら、「二極管」とか「三極管」という言葉に聞き覚えがあるはずだ。しかし、技術家庭科の教科書を発行している東京書籍によると、その真空管の項目も1978年度から削除されてしまったという。
「ラックスマン」のブランドで知られる「ラックス」(東京・東品川)が、復古調のデザインで真空管アンプを売り出したのは1995年秋。価格は35万円。ミニコンポが量販店で数万円で手に入る時代、決して安い買い物ではない。
ラックスも2年間で1500~2000台程度の生産を見込んでいたが、発売してみると、わずか半年間で1000台を売り上げた。販売促進部長の小川敏郎さん(49)は「正直言って驚いている。アンプの性能が向上して、音の“切れ”はよくなったが、“丸み”がない。その点、真空管は人の声や弦楽器を“柔らかく”再生してくれる。仕組みもわからないパソコンやワープロの操作を迫られている中高年が、そんな“テクノストレス”からの解放を、昔懐かしい真空管に求めているのではないか」と分析する。
復帰参入を果たしたラックスに対し、これまで真空管アンプマニアの市場を支えてきたのは、わずかな従業員で細々と作り続けてきた町工場だ。
その一つ、「マックトン」の社長、松本健治郎さん(64)の自宅兼仕事場は、環状八号線近くの東京・杉並区内の住宅地にある。玄関横の6畳ほどの居間がオフィス、その奥の4畳半が作業場。特大の試聴用スピーカーのほか、工具や部品が所狭しと並べられている。
会社設立は1964年。中学時代から電気回路に興味があったという松本さんにとって、真空管いじりは日課の一つだった。電機メーカーに勤めていたが、自ら設計した真空管アンプを売ってみたいと思い、脱サラの道を選んだ。
当初は十数人の従業員を雇っていたが、世の中は一気にトランジスター時代に。やむなく、大幅に規模を縮小し、社長一人で組み立てる「手作り品」の製作に転換せざるをえなかった。肝心の真空管も手に入りにくくなり、商社を通じて海外の在庫品を購入しては細々と操業を続けた。
息を吹き返したのは、東欧の民主化やソ連崩壊で、東側の軍事用真空管が西側に流出したのと、中国の真空管生産が軌道に乗った1990年代に入ってからだ。中高年ばかりでなく、真空管を知らない若い世代からも、製品カタログの問い合わせが来るようになった。
電源を入れると、むき出しの真空管に赤い灯がともる。アンプのデザインも手作り感覚がにじむ。
「真空管アンプは回路も簡単。少し知識があれば、故障しても、すぐに直せる。LSIではそうはいかない。手触りというか、自分で理解できる点が受けて、電気製品の原点みたいな真空管が復活してきたのではないか」と松本さん。
自社ブランド「マックトーン」は、1台39万円からと、これまた安くはない。独自の販売ルートを持たず、全国10か所くらいのオーディオ専門店の注文に応じて、宅配便で出荷しているが、月産6~7台のペースだ。
運輸省航空事業課長の丸山博さん(47)は、自作の真空管アンプでイタリアオペラを鑑賞するのが何よりの楽しみだ。1994年、ふと「アンプ作り」を思い立った。休日になると東京・秋葉原の電気街に通い詰め、部品集めに半年を費やした。いろいろな回路見本を参考にしながら組み立てるのにさらに半年。結局、1年掛かりの“工作”になってしまった。費用も20万円ほどかかったが、「真空管を使うと、弦楽器がふわっと響き、歌声も柔らかい。オペラにはうってつけなんです」。難題を抱え込んだ時に、自作のアンプでオペラを聴くのが、丸山さんの最高の気分転換だ。
そんなマニア向けに1996年3月初め、秋葉原で真空管だけを販売する専門店「クラシック コンポーネンツ」が新たにオープンした。店内にはさまざまな形をした約300種類の真空管がずらりと棚に並ぶ。1本数百円から3万5000円まで。
「客層が限られているので採算がとれるかどうかわからない」とマネジャーの浅野三千男さん(42)。おっかなびっくりの開店ではあるが、もちろん勝算がないわけではない。この真空管ブームを、“本物”と読んでのチャレンジだ。
真空管アンプ 観音堂で聴く きょう那古寺で鑑賞会 館山の佐久間さん製作
2009年10月10日、中日新聞
【千葉県】館山市那古の那古寺観音堂で2009年10月10日、自作真空管アンプ製作者として全国的に知られる洋食店経営佐久間駿さん(66)=千葉市北条=の真空管アンプ鑑賞会が開かれる。千葉市制施行70周年記念事業で、主催する千葉市教育委員会は「平成の大改修を終えたばかりの観音堂で深まり行く秋を感じながら、真空管アンプが奏でる音色を心ゆくまで楽しんでほしい」とPRしている。入場無料。
佐久間さんは千葉市内でレストラン「コンコルド」を経営する傍ら、真空管アンプの製作を趣味にしている。これまで奈良の中宮寺や高野山大講堂などで、真空管アンプのオーディオコンサートを開催。パリや米国シアトルでもコンサートを開くなど海外でも活躍している。オーディオの専門誌にコラムを連載し、真空管アンプの世界で知らない人はいない。
真空管アンプは、現在主流のトランジスタ(音声信号増幅器)が発明される前に、テレビやラジオなどのオーディオ製品に使用された。トランジスタと比べ音がやわらかく、耳になじむと根強いファンがいる。
鑑賞会は、千葉市が佐久間さんに打診して実現。真空管アンプと業務用の大型スピーカーでシャンソン、クラシック、ジャズ、歌謡曲などを再生する予定。
会場の那古寺は717(養老元)年、僧行基が創建したと伝えられる真言宗智山派の寺で、坂東三十三カ霊場の結願(けちがん)寺。鑑賞会のタイトルは「南総一の名刹(めいさつ)に球が灯(とも)る夕べ」で午後4時半開場、午後5時開演。佐久間さんは「コンサートは曲の説明などもするので午後9時ごろまでかかると思う」と話している。
真空管アンプ 光れ 自分だけの音
2017年5月15日、読売新聞
Styleプラス
奥行きがあってふくよか--。真空管アンプが奏でる音色に魅せられる人は多い。実験器具を思わせるガラス管がほのかに発光する様子には独特の美しさがある。
真空管は微弱な電気信号を増幅する装置で、真空で金属を熱すると電子が大量に発生する仕組みを利用している。
オーディオ部品などとして1970~1980年代まで日本やアメリカで大量に生産されたが、安価で消費電力の少ない半導体にとって代わられた。現在流通しているのは、備蓄されていたものや今も生産を続ける中国、ロシア製が主だ。
真空管アンプを見かける機会は減っているが、「音が自然」「艶がある」などと根強い人気がある。東京・秋葉原の「オーディオ専科」では、真空管の販売のほか自社製作のアンプも取り扱っている。
「FOX-BAT」(税抜き12万2500円)は、旧ソ連の戦闘機ミグ25にも使われていたとされる真空管を用いたという。左右対称のすっきりしたデザインが人気。「PROFESSOR-2」(税抜き13万6000円)は、音のゆがみや雑音が少ないと好評だ。
店長の森川雄介さんによると、部品を買い集めアンプを自作する人も多い。「どの音域を重視するかなど好みは人それぞれ。真空管を付け替えたりしながら、自分が求める音に近づけていくところに醍醐(だいご)味があるようです」と話す。
千葉県館山市の佐久間駿(すすむ)さん(74)はレストラン経営の傍ら、150種類を超える真空管アンプを製作してきた。半年ごとに、新作アンプによる音楽鑑賞イベントを開く。「真空管アンプの魅力は豊かな中低音。柔らかくて優しい音色は聞いていて疲れない。理想は、曲ごとに最適なアンプを用意すること。まだまだ作り続けたい」
真空管アンプには、デジタル製品にないぬくもりがある。「オーディオ専科」の森川さんは「熱せられた金属が光を発し、音を増幅させようと働いているのが目でもわかる。そうした手応えが感じられるのも魅力」と話す。
最近は、スマートフォンにつないで楽しむ、持ち運び可能な真空管アンプも登場している。イーケイジャパン(福岡県)の「TU-HP01」(税抜き1万9000円)。その音は、真空管を知らない「デジタル世代」にどんなふうに響くのだろうか。
「再生」もアナログに光
アナログ式の「録音再生機器」と言えばレコードプレーヤー。こちらも近年、人気が高まっている。
東京・秋葉原の「ダイナミックオーディオ トレードセンター」は、最盛期の1970年代に国内外で生産された状態の良い中古品や最新の上位機種などを扱っている。
レコードプレーヤーは年配の人には懐かしく、若い人には新鮮に感じられ、ちょっとしたブームだ。ダイナミックオーディオ トレードセンターでも随時、試聴会を開くなど力を入れている。企画担当の佐藤泰地さんは「アナログ式のオーディオには、音楽そのものだけでなく、その場の空気感まで再現する力がある。音楽好きをワクワクさせるロマンがある」と話す。
中には、100万円を超える高級品もあるが、大切に手入れをしていれば、何十年と使い続けられるという。「しっかり作られた良いものには、世代を超えて愛される魅力が備わっている」と語る。
真空管アンプ 自作キット人気 豊田自動織機子会社が販売=中部
2010年6月18日、読売新聞
トヨタ自動車グループの豊田自動織機の子会社、サンバレー(愛知県刈谷市)が企画・販売している「真空管アンプ」の自作キットが団塊の世代を中心とした音楽ファンの間で人気を集めている。豊潤で温かみがあるという独特な音色と、自ら作り上げる達成感が人気の秘密のようだ。
社内提案が発端
真空管アンプは、レコードやCDから得た微弱な電気信号を真空管を利用して増幅し、スピーカーを鳴らす装置だ。1960年代に入って、より低消費電力で、簡単な仕組みのトランジスターを使ったアンプが台頭。国内メーカーは、耐久性で劣る真空管アンプの生産中止を余儀なくされていった。
サンバレーは、もともと豊田織機の社員向けに日用品を販売する会社だが、1998年に、音楽ファンで、社員の大橋慎(まこと)さん(45)(現取締役)が「モノづくりの楽しさを真空管アンプのキットの販売で伝えたい」と社内で提案。当時の社長に「面白い」と認められ、自ら事業にかかわることになった。
大橋さんは、小学校時代からはんだごてを持ち、ラジオを製作していたオーディオマニア。良い音を鳴らすためのアンプの企画は大橋さんが行い、自作キットの部品は、約30社のメーカーから調達している。
1998年の販売当初は、3か月間も問い合わせが全くなかったが、音楽雑誌などに広告を出してファンを開拓。2002年にインターネット販売を始めると、人気に火がつき、販売台数は2002年度の約2000台から2007年度には約6000台と3倍に伸びた。
団塊世代つかむ
サンバレーの推計では、真空管アンプ市場の約4割を占めるトップ企業に成長した。
躍進の秘訣(ひけつ)は、モノづくりの楽しみにある。電子部品をはんだ付けしたりしてキットを組み立てる。特に子供のころ真空管のラジオをつくり、その音色に親しんだ団塊の世代の心をつかんでいるという。
2010年6月の5~6日には東京・秋葉原で試聴会が行われ、約300人が参加した。神奈川県海老名市の森裕君(ひろきみ)さん(52)は「完成して音が鳴った時は、我が子が生まれたようにうれしかった。作り方を教え合ったり、ファン同士の輪も広がった」と手作りの音の醍醐(だいご)味を語る。
ネット販売によって経費を徹底的に削減、価格も比較的安価なのも特徴だ。真空管アンプの価格は高いもので数十~数百万円もするが、サンバレーの売れ筋は10万円前後と値ごろ感もある。
大橋さんの目標は「団塊の世代に限らず、真空管アンプを多くの人に楽しんでもらう」ことだ。現在は、愛知県刈谷市にしかショールームはないが、東京にも出店するのが夢だ。問い合わせは、サンバレー通信販売専門店「ザ・キット屋」まで。
関連記事
ソニー、新たな船出--創業者の盛田昭夫氏亡き後、デジタル化へ本腰
1999年10月
ソニーの名誉会長、盛田昭夫さんが亡くなり、故・井深大(いぶかまさる)さんに続いて偉大な創業者が世を去った。2人の強烈な個性とリーダーシップで、「SONY」は誰(だれ)もが知る世界ブランドに育ったが、今やデジタル化とネットワーク化の波が押し寄せる激しい競争に直面している。精神的支柱なきソニーは新たな航海に乗り出した。
ヒット商品の現実
盛田さんが残した最大のヒット商品といえば、「ウォークマン」。全世界の累計出荷台数は1億8600万台(1998年度末、カセットタイプのみ)。世界中の若者を魅了し、生活スタイルを変えたのは事実である。1999年12月には、デジタル技術を取り入れ、テープに代わって半導体メモリーに音楽を記録する「メモリースティックウォークマン」として生まれ変わる。
しかし、これはソニーが自ら主導権を発揮して生み出した商品ではない。インターネットとデジタル圧縮技術(MP3=エムピースリー)を使って、ネット上でも送受信できる音楽データを活用した新興メーカーの携帯型プレーヤーを、追撃する商品なのだ。ウォークマン単体では、もはやもうけられない厳しい現実を示している。
撤退そして巻き返し
デジタル化とネットワーク化。急速に進む技術革新の荒波の中で、ソニーは、盛田さんら創業者が築き上げたアナログ技術中心のAV機器では、技術的優位を保てなくなってきた。「エレクトロニクス製品を売って利益を上げるビジネスからの脱皮が課題だ」と出井伸之社長も力説する。
盛田さんも実は、現在のソニーの姿を予感していたようだ。1987年に出した著書「メイド・イン・ジャパン」の中で、1960年代に電卓事業から撤退したことなどを例に引いて、「デジタル技術に関して、わが社は一歩、後れをとった」と述懐している。事実、ソニーはパソコンビジネスでは何度も失敗し、1997年7月に再参入した「バイオ」でようやく巻き返しに出たばかりだ。
創業時と違う企業に
ソニーの社内は、盛田さんの死去を冷静に受け止める。「ある種、伝説の中の人」と41歳の中堅社員。2000年3月には、ネット対応の新型家庭用ゲーム機「プレイステーション2」を発売する。「盛田さんは生前、プレステなんて名前は駄目だ、と文句を付けたこともあった」(出井伸之社長)が、今や連結決算での営業利益の4割を占め、ハードからの脱皮を図るうえでの戦略商品だ。
大賀典雄会長は仮通夜が営まれた1999年10月3日夜、「井深さんが始めた会社を、世界の優良企業にする基盤をすべて作ったのは盛田さんだった」とたたえた。一方で、「新しい21世紀型のソニーにしていかなくてはいけない」と付け加えることも忘れなかった。
ビジネス・リポート~ソニーを支える井深イズムの神髄
1998年1月
「人のやらないものをやる」「大衆が喜ぶものをつくる」――。
こうした理念を掲げたソニー創業者、井深大氏が1997年、亡くなった。
ソニーの強さの一因が、井深イズムの継承にあることは疑いない。
創業者精神の本質を、ソニーはどうやって継承してきたのか。
創業者亡き今、ソニーの進むべき道を探る。
ソニーが創業51年目を迎えた1997年は、その図抜けた強さと勢いが、ひときわ目立った年だった。
1997年3月期の連結決算は、売上高5兆6631億円、営業利益3703億円、純利益1395億円といずれも過去最高を記録した。デジタルビデオカメラやミニディスク(MD)プレーヤーなどのデジタル化されたAV(映像・音響)製品が国内外で急伸した1997年も好調は続き、1998年3月期の連結決算では、再び過去最高となる売上高6兆3000億円、営業利益4750億円、純利益1850億円を見込む。欧米で重視される経営指標である連結株主資本利益率(ROE)も、2期連続で10%を超えるのはほぼ確実だ。
この好調を受け、ソニーの株価もうなぎ登りに上がっている。1997年初頭に7000円台だった株価は、いまや1万1000円から1万2000円台へと急騰。時価総額も膨れ上がり、1997年8月には初めて日立製作所を抜き、10月には松下電器産業をも追い越した。
業績だけではない。「SONY」というロゴは今日、日本や米国、欧州はもちろん、アジアやアフリカに至るまで世界のどこでも、目にすることができる。「SONYはいまや、世界で最も価値あるブランドの1つになった」という大賀典雄・ソニー会長の主張には、疑念を差し挟む余地はない。
「インテル、マイクロソフト、IBM、モトローラ、ヒューレット・パッカードこそ、ソニーのライバル。日本企業ではない」――出井伸之社長のこの口癖を単なる驕りと受け取る人は少ないはずだ。終戦後の焼け野原跡の町工場からスタートした中小企業が、50年を経て世界に冠たる優れた企業に育った。
その原動力になったのが、1997年末、亡くなった創業者、井深大氏が自ら実践してきた「井深イズム」といえる。
「人がやらないものをやろう」
「創業当初は食えなくてね。NHKの仕事を引き受けたりして食い扶持を稼いでいました。ですが、井深さんはそのときから、大衆が喜ぶ製品をつくりたいと常々言っていた。ウチは新興だから、人がやらないものをやろう。そうして日本の復興に貢献しようと」
ソニーの創業メンバーの1人で、現在もソニー相談役の樋口晃氏は、井深氏が示した考えをこう振り返る。
この井深氏の想いは、1946年にソニーの前身である東京通信工業を設立した際に、井深氏自らが起草した設立趣意書によく表れている。そこにはこう記されている。
「一、不当なる儲け主義を廃し、あくまで内容の充実、実質的な活動に重点を置き、もっぱらに規模の大を追わず」
「一、経営規模としてはむしろ小なるを望み、大経営企業の大経営なるがために進み得ざる分野に技術の進路と経営活動を期する(後略)」
実際の設立に際して、井深氏はせっかく記したこの趣意書の存在を忘れ、自分の言葉で設立の挨拶を述べた。だがその話の内容は、後年、発見された趣意書とほとんど同じであったという。趣意書に示された考えは、井深氏の信念そのものだったといえる。
さらに樋口氏は、井深イズムのもう1つの特徴として、スピード重視と自由の尊重を挙げる。
「とにかくスピード重視で次から次へといろんなことに挑戦する。失敗も厭わない。後で取り返せばいいやという感じでね。朝令暮改どころか朝令朝改になるもんだから、それが嫌な人は随分、ソニーを離れましたよ」
「でも井深さんは上下の分け隔てをしなかった。自ら現場に降りて士気を鼓舞はしますが、開発陣には好きに研究させていた。そのせいか、社内全体がとても自由闊達な雰囲気でした。だから派閥もできませんでしたね。ソニーに残った人はみんな井深さんを慕ってましたよ」
学生時代からフランス行きを切望していた出井氏が、ソニーの入社面接で「フランスに行かせてくれないのなら入らない」と言い放って入社したという話は有名だ。しかし、樋口氏は面接したはずの出井氏のことをよく覚えていないという。
「当時はね、無茶なことを言い放つ人間が目白押しでしたから。伝えられる出井さんのセリフは決して特別ではなかった。新しいことへの挑戦の連続で仕事は厳しかったが、それだけ社内は自由だったんです」
この厳しさと自由闊達さのなかから、家庭用ビデオテープレコーダーなど数々の新製品を開発した木原信敏氏(現ソニー木原研究所長)や、トランジスタの研究中にトンネル・ダイオードの原理を発見し、ノーベル賞を受賞した江崎玲於奈氏(現筑波大学学長)ら優れた研究者が次々と育っていったのだ。
世界初のトランジスタテレビ開発
とにかく人のまねはせず、人のやらないことをやる。それも周囲の人間に自由を与え、その才能を引き出しながら、スピーディーにだれよりも早く実現させようと努力する。そして大衆に喜ばれる製品をつくる――。井深氏自身がアイデアを発し、開発に携わってきたソニー製品をみていくと、井深氏が目指したことがよくわかる。
1948年ごろ、かねてからの念願だった民生用製品に挑戦しようとした井深氏が最初に挑んだのは、当時、最も商売になりそうだった真空管方式のラジオではなく、国産初となるテープレコーダーの開発だった。
次いで取り組んだのは、米ウエスタン・エレクトリック(WE)社から製造特許を得て、日本ではだれもやったことがないトランジスタを開発し、それを使ったトランジスタラジオを世に送り出すことだった。
トランジスタラジオの開発そのものではタッチの差で米国企業に先を越されたが、負けじと今度はワイシャツのポケットに入るような超小型トランジスタラジオで世界初を達成。さらにラジオに続き、世界初のトランジスタテレビも開発し、先陣を切って発売にこぎつけた。当時の通産省がWE社の製造特許の導入許可を出してからトランジスタラジオの発売まで1年半足らず。最初のトランジスタテレビの完成・発表までも、わずか6年しかかからなかった。
白黒トランジスタテレビに力を入れた結果、他社から出遅れたカラーテレビでも、井深氏は未開の分野に挑戦する姿勢を貫徹した。当時、実用化に最も近かった米RCA社のシャドーマスク方式を他社が軒並み採用するなか、敢然とこれに背を向け、独自方式のカラーテレビ開発に踏み切った。
こちらも1961年3月に米ニューヨークの展示会でクロマトロン方式のブラウン管を見てから、試行錯誤の末、トリニトロン方式カラーテレビを発売するまで、わずか7年半しかかかっていない。
井深氏のように明確な理念を持ち、行動的でもある創業者を持つ企業は、ソニーに限らず決して珍しくない。ところが、多くの普通の企業の場合、当初はソニーのように成功を収めても、企業規模が拡大し、創業者が経営の一線から身を退くと、創業者が掲げた理念を忘れ、活力を失い、冒険を恐れ、保守的な判断を尊重する事なかれ主義の大企業へと変身していってしまう。
実際、ソニーにも、井深イズムという創業者精神を失いそうな危機が少なからずあった。だが、直面したこれらの危機をことごとく乗り越えてきた。なぜなら、井深イズムを受け継ぐ仕掛けを、絶えず組織のなかに埋め込む努力を続けてきたからである。
井深イズムを受け継ぐ仕掛けの最たるものは、“挑戦”を常に掲げる経営者の姿勢そのものである。(構造化知識研究所)
井深イズム受け継ぐ後継経営者
井深イズムを受け継ぎ、さらに拡大していったのが、創業時から女房役として井深氏を支え、1971年6月に井深氏に代わってソニー社長に就いた盛田昭夫氏(現ソニー・ファウンダー、名誉会長)だった。
盛田氏の挑戦、それはソニーの製品を国際的に展開し、世界中でソニーブランドを確立することで、井深氏の挑戦を世界に知らしめることであった。
1955年、盛田氏はソニーという商標をつけた国産初の小型トランジスタラジオTR-52のサンプルを持って、渡米する。そこで盛田氏がやったことは、米の大手時計会社グローバー社から出された10万台にのぼるTR-52の受注を蹴飛ばすことだった。理由はただ1つ。グローバー社がソニーブランドを使わず、自社ブランドで販売することを条件にしたからだ。そこには「ソニーというブランドを絶対に世界中に知らしめてみせる」という盛田氏の強い意気込みが感じられる。
1960年2月には、ニューヨークにソニー・コーポレーション・オブ・アメリカを設立。次いで1961年2月には、日本の株式を米銀が預かり、代わりに代用証券を発行する米国預託証券(ADR)の形で、米国証券市場から直接、資金調達することにも成功した。
銀行借り入れという間接金融にしか頼れず、旧財閥に属さないためそれもままならない。この脆弱な財務体質を改善し、同時に米国での知名度を上げるという一石二鳥を狙った盛田氏が、自らADR発行のプロジェクト・マネージャーに就き、力を注いだ結果だった。日本企業では初めてのことだ。
ソニーにとって幸いだったのは、こうした井深氏、盛田氏という2人の創業経営者の挑戦精神が、決して衰えなかったことである。
1979年に発売され、全世界で一世を風靡した「ウォークマン」。実は、このウォークマンのような製品を欲しいと言い出したのは、当時70歳を超え、名誉会長に退いていた井深氏であり、試作された製品を商売にしようと世界を駆け回ったのは、1976年に社長職を岩間和夫氏(故人)に譲って会長に就いた62歳の盛田氏だった。普通ならば老け込み、守りに入る年齢になっても、自分たちの夢に挑戦し続けた。この姿が、ソニー社員に与えた影響は大きいだろう。
岩間氏が急逝した後、社長に就いた大賀・現会長や、出井・現社長にも、井深イズムは浸透している。
大賀氏は、アナログが当たり前だった音楽の世界にデジタルメディアであるCD(コンパクトディスク)を持ち込み、これを世界へ普及させることに力を注いで実現した。
大賀氏の後を継いだ出井氏は、デジタルとインフォメーション・テクノロジーを事業のキーワードに据え、本業であるエレクトロニクス製品(ハードウエア)と、映画・音楽・ゲーム(エンターテインメント)に加え、その間を結ぶ流通経路になるデジタル衛星放送や広告業にも進出、「娯楽事業の川上から川下まですべてを押さえる世界で唯一の企業グループを目指す」という姿勢を打ち出した。
だがこうした経営トップの行動は、創業者精神を継承する必要最低限の条件ではあるが、これだけでは十分とはいえない。ソニー精神が衰えなかった理由は、井深イズムの継承を担保する仕掛けを、うまく制度化し、運用していったところにある。
その代表が、組織図が役にたたない組織と、自己申告異動制である。
ソニーでは頻繁に人事異動がなされ、組織が改変されるため、1度つくられた組織図はすぐに古くなり、役に立たなくなってしまう。
社内公募と自己申告異動制で活況
組織に人をはめ込むのではなく、個人個人の資質を見極め、その人物に適した仕事を割り当てる。その人物に適した仕事がなかったら、新たに部署を設けることも厭わない。そうして優れた人物の才能を引き出しながら、未知の領域に挑戦を続ける。規模の小さな中小企業ならともかく、大企業にはなかなか難しいこの手法を、ソニーは今も実践し続けている。
1996年10月に発売し、現在も売れ行き好調な携帯型MDプレーヤー「MDウォークマンMZ-E50」の開発にも、人を優先するこの組織づくりが生かされた。
開発を指揮する福島貴司統括部長は、自ら人事部に乗り込み、これはと思う67人をリストアップし、手元に集めて開発のためのプロジェクトチームを新たにつくったのだ。「各部門の担当役員を回り、上から説得して強引に集めたので、あちこちから恨まれた」(福島統括部長)とはいえ、それを可能にしてしまうのが、ソニーの組織づくりのうまさなのである。
上からの評価を待つだけでなく、社員自ら「こういう仕事をやりたい」とアピールすることもできる。
ソニーでは社内のどの部署でも、社内報で社員を公募することができる。これを見た社員は、公募に応じる。採用する部署と申告した本人の希望が合致すれば、手を挙げた社員の上司がどんなに反対しても、異動は実現する。
家庭用ゲーム機「プレイステーション」を世界中で2500万台販売し、1998年3月期には前期比60%増となる売上高6500億円を稼ぐ見込みのソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)。1994年の設立にもかかわらず、数字のうえでは、ゲーム業界の主と恐れられた任天堂をも凌駕しつつある。SCEには創業時、技術部門から管理部門までソニーから数多くの人々が、自己申告異動制を使って出向している。
「最初は人手が足りなくてね。ソニーの人事部にいやがられるほど社内公募をかけたんです。そうしたらやる気に満ちた人がかなりきて、生き生きと仕事をしてくれた。彼らがいなかったら、SCEの成功はなかったでしょう」
徳中暉久・SCE社長は、自己申告異動制がいかに社員のやる気を引き出すかを強調する。
普通の会社ならば、手を挙げた社員が非難を受けそうだが、ソニーの場合、批判を受けるのは元の上司だ。やりたい仕事、つまり挑戦の機会を部下に与えなかったと見なされるからである。やる気のある社員にとって、これほど恵まれた職場はないだろう。
井深イズムを継承するさまざまな仕掛けをつくり、井深イズムを大きな拠り所として日本を代表する国際企業へと成長を遂げてきたソニー。しかし、井深氏が亡くなった今後はどうだろうか。
井深氏は経営の一線を退いていたし、ソニーの経営に与える影響はそれほど大きくないという見方はある。だが、創業者の持つ重みは、創業者が生きているという事実だけで確実に大きいものだ。井深氏が亡くなったいま、ソニーの精神的拠り所が、ある程度、揺らぐことは避けられないだろう。
出井氏の打ち出した総合娯楽企業グループを目指すという方針は、ハードウエアを中心にしてきたソニーにとっては未知の分野への挑戦である。
しかし、井深氏が亡くなった後も井深イズムを継承し、さらにこれを乗り越えていくためには、挑戦するだけでは十分ではないだろう。新たな挑戦を成功に導き、挑戦を尊ぶ井深イズムがやはりソニーにとっての王道なのだとグループ従業員や株主に納得させることが不可欠になる。そうして初めて、ソニーの未来が開けるはずだ。
出井氏の新たな挑戦が成功するかどうか――出井氏が“確実な成功”という重い課題を背負ったことだけは間違いない。